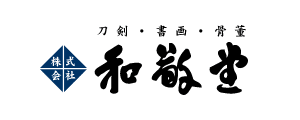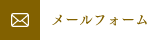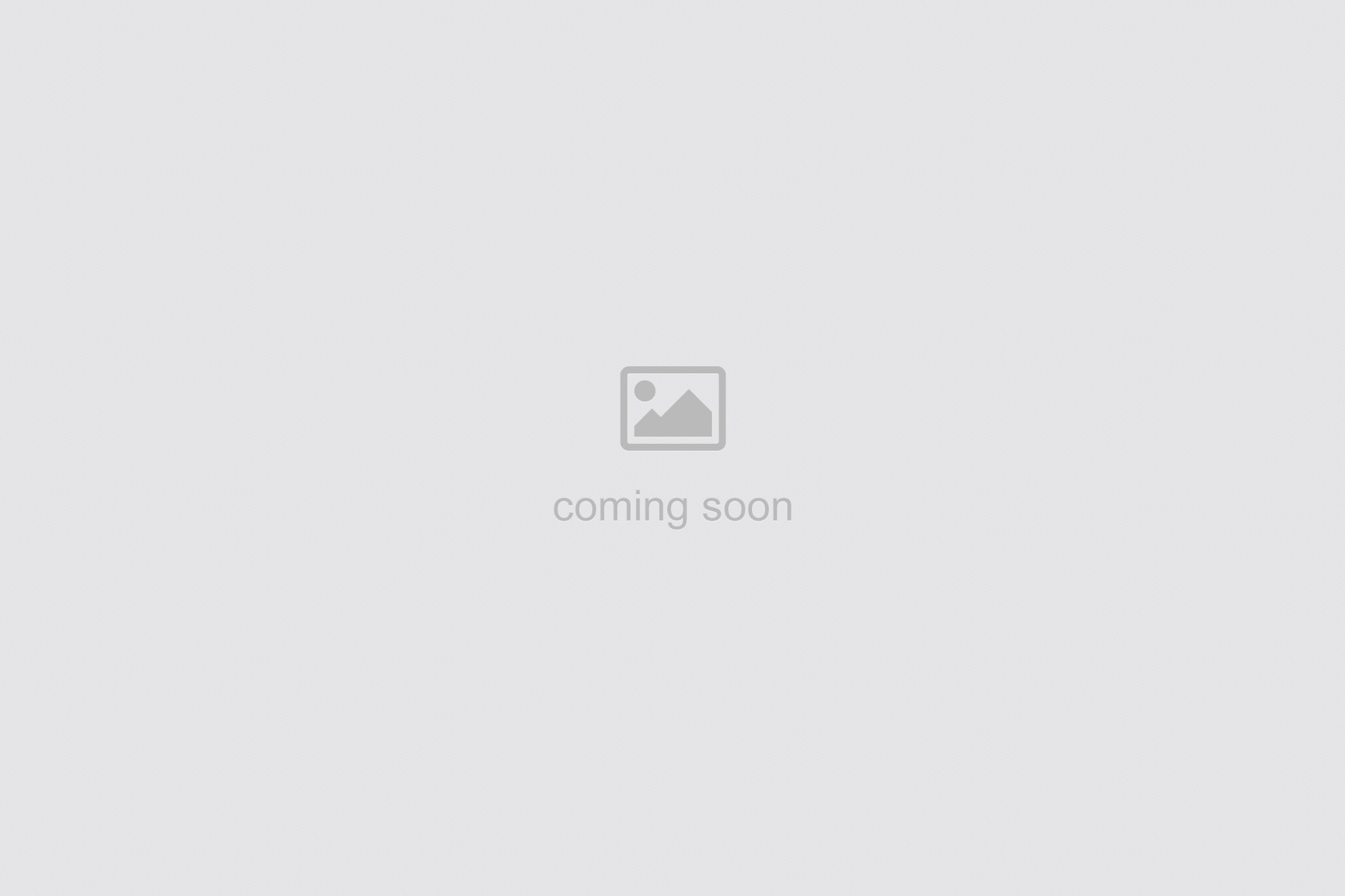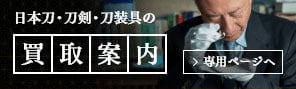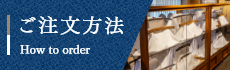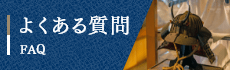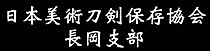品番 A350521
銘文 和泉守藤原兼定(会津十一代)
於越後国加茂造
Sign Izuminokami fujiwara Kanesada (Aizu11th)
Echigonokuhi kamo ni oite tsukuru
価格 売却済
price Sold
鑑定 財)日本刀剣保存協会 特別保存刀剣
Certif [N.B.T.H.K] Tokubetsu Hozon Touken
登録 茨城11203
寸法 長さ 二尺三寸一分強(70,2m) 反り1,0cm 目釘穴 1個
Size Blade length 70,2cm Curvature 1,0cm Mekugi 1Hole
国 会津
Country Aizu
時代 明治初期
Period first of Meiji
形状 鎬造り、庵棟、身幅重ね頃合い、反り浅くつき、中切先伸びこころとなる
鍛え 小板目肌よく詰んで、所処大肌混じり、地沸つく
刃文 直刃調に僅かに湾れ、互の目交じり、小沸出来となり、匂口深く冴える
帽子 先やや掃きかけ丸く返る
中心 生ぶ、先刃上がりの栗尻、鑢目筋違い
白鞘 有
解説
会津十一代兼定は三善長道や角元興らと共に会津を代表する刀工である。
新選組の副長、土方歳三の愛刀であったことも知られており、その切れ味は相当のものであったと伝えられている。
会津の兼定は室町期の関の兼定が慶長ごろに会津藩の蒲生氏郷の鍛冶になったのを初代とし以降幕末まで繁栄し十一代兼定はその最後を飾る良工である。
十一代兼定は天保八年に生まれ十四才のときから十代兼定について鍛刀を学び初銘を兼元と切る。その後京都に上り修業をし和泉守を受領し慶応元年に会津に帰る。
本作は明治初期の加茂打ちの刀である。十一代兼定はこの時期に加茂の有力者からの注文で加茂で作刀してるが、短刀の数が多く、刀の数は比較的少なく貴重。
やや大肌が混じった精美な地鉄にやや焼きが低く、小沸出来の匂口の深い刃は如何にも切れ味が良さそうで、幕末から明治にかけた実践的な機能美はさすが兼定の逸品である。
お問い合わせ・ご注文はこちらから
お電話でのお問い合わせはこちらまで
0258-33-8510
お気付きの点、ご不明な点がございましたら
お気軽にお問い合わせくださいませ。